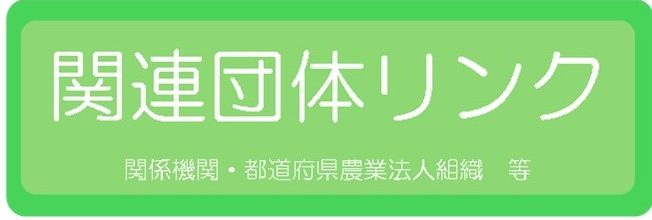活躍する日本農業法人協会の会員を紹介します
会員限定の情報紙「Fortis秋の特集号」から、活躍する日本農業法人協会の会員をご紹介します。
強みを生かす経営を実践!次世代農業サミットをもっと刺激的に
徳島県
アイ・エス・フーズ徳島株式会社
代表取締役 酒井 貴弘
アイ・エス・フーズ徳島(株)は、徳島県阿波市で青ネギを栽培し、主にカット工場向けに販売する農業法人だ。代表取締役の酒井貴弘氏は、23歳で同社を設立。現在は、従業員数40名(外国人技能実習生含む)の規模まで成長させた。また、当協会の若手農業者向けイベント「次世代農業サミット」には第1回目から参加しており、2023年4月に2代目の実行委員長に就任した。今回は、酒井氏に同社の歩みと、今後のサミットへの意気込みを聞いた。
就農1年目で売上1億円を達成
兵庫県淡路島で、水稲とタマネギの兼業農家に生まれた酒井氏は、学生時代は野球に打ち込んだスポーツマンである。そんな酒井氏が就農したのは20歳の時。きっかけは父親からの誘いだった。
父親は友人と淡路島で青ネギ栽培を始め、法人化のタイミングで酒井氏を誘ったという。既に6千万円ほどの売上があり、「面白いと思った」と酒井氏は話す。
当時は、某うどんチェーン店の関東進出を背景に、青ネギの市場規模が急拡大していた。法人化1年目で売上は1億円を超え、2年目、3年目も売上は順調に伸びた。しかし淡路島は農業が盛んで、農地の確保が難しくなっていた。また、台風や病害虫の被害も受け、産地を一カ所に固める事にリスクを感じていたという。そんな折、徳島県の契約農家から土地が余っていると聞き、酒井氏は、分社化と徳島県への移住を決意した。ちなみに、分社化(独立)の背景には、父親との衝突もあったそうで、「父親から離れて自分の力でどれだけの経営ができるかを試してみたかった」と酒井氏は振り返る。
独立し、徳島県へ移住
弱冠23歳で独立し、2017年6月にアイ・エス・フーズ徳島(株)を設立した酒井氏だが、やはり農地の確保には苦労したという。当初は「こんな若い子に農業ができるわけがない」「知らない人に貸したくない」と断られてばかりだった。最終的には、ある農機メーカーの紹介で、ようやく20aの耕作放棄地を借りることができた。しかし、酒井氏への試練は続く。初めての収穫目前に、10月には珍しく2週連続で台風が来てしまう。そしてその冬は雪も積もったのだ。
順調だった淡路島時代に比べかなり厳しい状況にも思えるが、酒井氏は「1年目の経験のおかげで免疫ができ、僕の中ではすごくよかった」と振り返る。
農地をきれいに管理し、品質の良い青ネギを栽培することで、徐々に地域の信頼を得ていった。どんどん農地も集まるようになり、人材確保にも力を入れた結果、設立3年で見事に売上1億円を達成した。
強みを生かして組織力アップ
しかし、規模拡大とともに組織運営の壁に直面する。そこで酒井氏は、現場を離れることを決断。経営スキルを磨きながら、改革に取組んだ。その一つが「強み分析」である。例えば、酒井氏の強みの一つは「未来を描く力」だが、それまでのプロセスを描くのは苦手。幹部には、酒井氏の苦手な部分を補い合えるメンバーを配置した。人員配置のほか、仕事の振分けにも活用しており、「得意なことを任せると仕事も捗るし、本人も楽しい」と、酒井氏は導入後の変化を実感する。
生産部門は、生産部長と農場長が担っている。なんと同社の青ネギの収穫量は、他の農業法人と比べ1.5~2倍だという。その秘訣は、圃場130枚すべてに実施する土壌分析と、その結果に合わせた施肥設計だ。「植物の生育を正しく理解した上で、栽培管理に応用することがポイント」と酒井氏は教えてくれた。もともと感覚的な農業が嫌だったという酒井氏。経営を可視化するためにASIAGAP認証も取得した。「僕一人ではできなかったが、論理的で分析が得意な社員が形にしてくれた」と笑顔で話す。
急成長を遂げた同社だが、やはりその原動力は酒井氏のビジョンと実行力である。経営手腕はもちろん、周囲に影響を与える力強さと誠実な人柄で、同社をさらに進化させるに違いない。
次世代農業サミットとの出会い
そんな酒井氏と当協会のサミットの出会いは淡路島時代。サミット発起人である山田敏之氏(当協会 元会長)に、販売イベントで声をかけられたのが参加のきっかけだ。第1回サミットは「衝撃的で刺激的だった」と酒井氏は語る。淡路島の中では売上高も大きく、自身ではなかなかの農業法人だと思っていた。しかし、全国から集まった農業法人の層は厚く、「化け物みたいな人」ばかりだった。自分の視野の狭さを感じ、良い意味で居心地が悪かったそうだ。その後も継続して参加し、研鑽を積んだ。参加する度に人脈が増え、多くの学びを得たという。
ワクワク、メラメラ感のあるサミットへ
サミット実行委員には自ら志願した。「前委員長の鈴木貴博さんのもとで勉強したい。鈴木さんのリーダーシップを学びたい」と思ったからだ。そして今年、鈴木前委員長の推薦を受け、2代目の実行委員長に就任した。
「サミットに成長させてもらったので、貢献していきたい。参加者がワクワクし、やる気がメラメラ燃え上がるようなイベントにしたい」と酒井氏は意気込みを話す。
目下の課題は、売上3億円以上の農業法人の参加率低下だ。「1億円以下の参加者との間に温度差があるのではないか」と酒井氏は分析する。
現在、実行委員会では、来年2月開催のサミットに向け、企画立案の真最中である。参加者全員の成長意欲・向上心を掻き立てるべく、「目線を高く設定し、大きな農業法人にも意味のあるイベントにしたい」と酒井氏は熱く語る。
取材後も、「企画のアイデアはいっぱいある」と話してくれた酒井氏。サミットの詳細は12月を目途に発表予定だ。若手農業者の皆様は、ぜひ日にちを空けて楽しみに待っていただきたい。
更新日:2023年11月2日